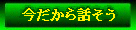▼高齢者なので… 高齢者の私は、日々 重力と戦っています。年寄りの“愚痴”だと思って読んでください。 先ず、足が重くなりました。腰も重いし、肩も重い。そして最近は口も重くなってきています(これは以前からそうだったと言う人もいますが)。ものを食べるとき以外は口を開くのも億劫になってきました。 今や昼間でもまぶたが重くて重くて、普段は眼を細くしてその細い隙間から外の様子を見ているような感じなんです。 そういったいろいろな重みに耐えかねてか、全身の皮膚や筋肉も(重力のせいで下に向かって!)たるんできているのです。 気のせいでしょうか身長も少し縮んでしまったようです。普段は自分の身長など測ったりはしませんが、かかりつけ医のところへ行って計測すると、何と! 身長が短くなっているじゃないですか。今までは、白衣高血圧のように、医師の白衣を見て身が縮むような思いをしているせいだとばかり思っていたのですが、本当に短くなってしまったようです。これも重力のせいですよね。困ったことです。 更に困ったことがあります。 髪の毛が少なくなったなぁと思っていたら、実は頭部から顔の頬や顎の部分へと少しずつ移動(落下!)しているようなんです。多分 重力のせいではないかと疑っています。 齢を重ねると、こういう苦しみが待ち構えているとは知りませんでした。各々方、気を付けた方がよいと思いますよ。 ▼子供の頃は‥‥ ルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」を読むと、アリスが兎穴に落ちる場面では、初速度のままゆっくりと落下していく様子にわくわくしたものです。重力の加速度など存在しない世界だったようです。 思えば、重力の加速度など知らなかった子供の頃が懐かしいです。野外を自由に遊びまわっていた頃は実に楽しかったものです。高いところから跳べば下に落ちるのはごく自然なことであって、私は何の不思議も感じませんでした。重力などという概念を知らなくても、落下するのは当然のことと理解していましたから。 「詳しいことを書く余白がない」ので省略しますが‥‥ ▼高校時代‥‥ 重力の加速度を知ったのは高校時代でした。物体の落下速度は時間とともに加速度的に速くなるという事実を学んだのです。そのとき使われた時間の単位は“秒”でしたが、“年”の単位で考えることなどありませんでした。 しかし高齢者になってから気が付いたのですが、私の実感では“年”の単位で変化する側面にも目を向けるべきではないかと思うのです。これは、高齢者になって経験してみないと分からないことなんですけどね。 「詳しいことを書く余白がない」ので省略しますが‥‥ ▼厳しい現実の世界へ‥‥ 最近は学校の校舎の窓から、あるいはマンションの屋上から飛び降りたりする子供が増えてきています。重力の恐ろしさを若者たちに知ってもらう必要があると思います。 重力のことなど気にもしない若者たちに知ってもらうには、これはもう絶対に「アリスが兎穴に落ちる話」を持ち出して話すしかないと考えたのです。 しかし「詳しいことを書く余白がない」ので省略しますが‥‥ ▼教師となってプログラム作り‥‥ 教育現場での話ですからプログラムの名前は「アリスの墜落死」では悲惨な印象を与えてしまうので望ましくありません。そこで「アリスの墜落事故」程度で収めることにしました。 「詳しいことを書く余白がない」ので詳細は省略します。 ▼重力を逸らす方法 つまり重力というのは、放射線と同じように身体に過剰に浴びると健康には良くないのです。そこで、重力をできるだけ過剰に浴びないで済む方法「重力を逸らす方法」を紹介したのですが‥‥、5年くらい前に書いたのですが、残念ながら誰にも、ほとんど、いや20人位かな、しか読んでもらえなかった代物です。 関心のある方は、以下の掲示板から 「重力の恐ろしさ[Rewrite版]」を選んで読んでください。 |
2023年6月11日日曜日
重力の恐ろしさ
2023年5月14日日曜日
大谷伝説について考える

▼筋書きを作ったのは誰か? 2023年のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)が侍ジャパン優勝という劇的な形で幕を閉じてからもう2ヵ月以上が過ぎようとしている。私はスポーツ誌を購入して関係する記事を読んだり、ウェッブ上の記事や写真を見ては当時の記憶を思い起こして楽しんでいる。いつまでも飽きることがない。 SNS上では、最近はスポーツ関係の記事が多くなっているので、関心のあるテーマを見つけるとリンク先の元データの方を読む。アメリカのスポーツジャーナリストが書いた記事の紹介だったりすると英文記事の方を読みたくなる。 SNSの記事は入れ替えが激しいから、以前読んだ記事をそうとは気が付かずに繰り返し読まされることもある。しかし同じような記事を読まされていても一向に飽きることがないから不思議である。 WBCでの日本の勝利はあまりにも劇的過ぎて「一体誰がこの筋書きを作ったのだろう」と思うことがある。まるでマンガを読んでいるようだと言う人もいる。こちらの期待した通りに筋書きが進んで行くので、何かマンガ本の筋書きを見ているような気がしてくるからであろう。 4月になるとメジャーリーグの試合(MLB)も始まり・・・・・ |
2023年4月4日火曜日
2023年 今年も桜が咲きました

▼撮影データの例 
撮影データの例 ▼IMG_3921s.jpg 

IMG_3921s.jpg |
2023年3月4日土曜日
漫画家をめざした戦友たち

昔 男ありけり 手塚漫画に影響され 漫画家を志す 自分の未熟さを知り 早々に脱落 晩年に至り 昔の 名も知らぬ戦友たちを懐かしむ ゴールした戦友たちに拍手 漫画家の松本零士さんが亡くなられた。 新聞で有名人の訃報を伝える記事を読んでいると、自分が高齢者になったからだろうか、没年齢が気になるようになった。特に、漫画家の場合は年齢欄を見落さないように注意している。 松本零士さんの作品を、私は全く読んだことがない。そんな私がなぜ彼に注目していたかというと、それは私とほぼ同じ年齢層だったからである。年齢が近いことは以前から承知していた。 今まで私が関心を持った漫画家には以下の方々がいる。 生年 没年 (1)藤子・F・不二雄 (1933年12月1日 ~ 1996年9月23日, 62歳没) (2)石ノ森 章太郎 (1938年1月25日 ~ 1998年1月28日, 60歳没) (3)赤塚 不二夫 (1935年9月14日 ~ 2008年8月2日, 72歳没) (4)藤子 不二雄A (1934年3月10日 ~ 2022年4月7日, 88歳没) (5)松本 零士 (1938年1月25日 ~ 2023年2月13日, 85歳没) 参考のため日米の漫画の大御所についても記すと、 ・ウオルト・ディズニー(1901年12月5日 ~ 1966年12月15日, 65歳没) ・手塚 治虫 (1928年11月3日 ~ 1989年2月9日, 60歳没) 60歳台で亡くなっている方が多い。漫画を描くという作業は想像以上に厳しい仕事なのであろう。そんな中で藤子不二雄Aさんと松本零士さんは長生きされた方である。 私が関心を持っている(1)から(5)の方々は、漫画家の手塚治虫氏が若い頃に住んでいた“トキワ荘”の住人たちである。 |
2023年1月17日火曜日
エイプリルフールとうるう秒

小学生の頃、エイプリルフールといえば“嘘を付いてもよい日”と聞いていたので、私は毎年この時期になると張り切って嘘を付いて人をだまそうと思ったものだ。しかし普段から嘘ばかり付いている(?)のに、いざとなるとなかなか気の利いた嘘を思いつかない。そんなとき自分は生まれつきの正直者であるに違いないと思ったりした。いや…、そう誤解したのであった。 当時は、新聞のニュースやラジオの番組を通じて嘘が流され、それを真に受けた人たちが大騒ぎするのが後日談として報じられ人々を楽しませてくれていた。しかし最近はIT企業などの新興企業が中心になって、かなりの資金を投じて準備された嘘を流すようになってきている。それが会社の宣伝にもなると思ってのことであろう。最初から嘘に違いないと分かっていても、つい本気にして騙されたくなるほどの出来栄えであることがまた楽しい。 2016年のエイプリルフールの前日(3/31)、私は自分のホームページの4月分の更新作業をしていたとき、突然自分もホームページ上でエイプリルフールの嘘を仕掛けてみたくなった。小学生時代の楽しかった思い出がよみがえってきたのである。 |
2023年1月7日土曜日
2022年12月11日日曜日
スケジュール遅延の言い訳

── 裁判員制度旧版の【素歩人徒然(62)】「裁判員制度」(2008-1-1)の原稿は2007年末に書いたものですが、執筆当時はまだ守秘義務もあり詳しく書くことができませんでした。文章も未熟でした。その後【今だから話そう(2)】欄の「グリーンベレー」で仕事の詳細を報告しましたので、こちらの原稿も書き直すことにしました。タイトルも変えました(2022-12-9)。▼裁判員制度の導入 2009年春から日本でも裁判員制度が始まった。新しい制度の導入時には、私も自分がもし裁判員に選ばれたらどう対応したらよいかと考えるようになった。国民としての義務を果たしたいと思う反面、他人を裁くという行為では責任の重さについて悩むことになるのではないかとも思った。しかし、多分一番迷うのは当面の自分の仕事に対する影響から「辞退したい」という気持ちになるのではないか、という点であった。 当時、私は大学の教師をしていたので、裁判長との面談の際に「自分は教師をしているので、講義を休むことになれば卒業に差し支える学生も出てきます」などと情けない辞退理由を説明している自分を想像したりしていた(本当に情けない(!))。 裁判長は候補者と面接した後、別室で検察官、弁護人と協議し最終的に裁判員6名を決めるのだそうである。辞退しないでいて運よく(?)選ばれなかった場合でも、今度はなぜ自分が選ばれなかったのかとその理由を知りたくなるかもしれない。いずれにしても厄介なことである。 アメリカでも同じように陪審員制度というのがある。日本とはだいぶ様式が異なるが、仕事との関係ではやはり問題になることが多い。それにまつわる話をしてみようと思う。 |
登録:
コメント (Atom)